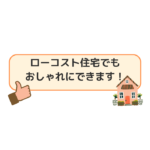「ローコスト住宅って、本当に住んで大丈夫?」「安かろう悪かろうじゃないの?」
私自身、そう思いながら情報を集めていたひとりでした。SNSで「やばい」「恥ずかしい」なんて声を見るたびに、一生に一度の買い物だからこそとても不安になったのを覚えています。
でも実際にローコスト住宅を建てて、家族と暮らし始めて今思うのは、「知っていれば防げる後悔も多い」ということ。そして、「コストを抑えつつ、納得できる暮らしはちゃんと実現できる」ということです。
この記事では、私の実体験をもとに、ローコスト住宅の仕組みやメリット・デメリット、住んでわかったリアルな本音まで正直にお話しします。これから家づくりを考えているあなたの参考になれば嬉しいです。
我が家のコンセプトは「子どもにもお財布にも優しい家づくり」です!
「おしゃれにしたい」「快適にしたい」「家事を楽にしたい」けど「できるだけ安くすませたい」
こんな価値観に合う方にきっと参考になりますので、ぜひ記事を見ていってくださるとありがたいです♪
目次
ローコスト住宅とは?まずは定義と特徴をやさしく解説
ローコスト住宅の定義
まずはローコスト住宅に聞き馴染みのない方に向けて定義を説明します。
ローコスト住宅の明確に定まった定義は今のところ無いのですが、一般的な注文住宅に比べて建築費用を大幅に抑えた住宅のことを指します。具体的には「坪単価30〜50万円前後」で建てられた家をローコスト住宅と呼ばれることが多く、坪単価30~50万円で建築可能な住宅メーカーをローコスト住宅メーカーと呼んでいます。
なぜ安くできる?材料・工法・人件費の違い
坪単価が数十万円安いだけで仮に30坪の家の場合数百万建築費用が変わってくるのでとても魅力的ですよね。
え!?そんなに安くで大丈夫なの?! と思う気持ちもあると思います。
一般的なローコスト住宅がここまで安いのかというと、実は使う材料や工法、設備、人件費の部分で大きな違いがあります。
たとえば、注文住宅でよく使われる無垢材や高性能の断熱材を控えめにし、比較的リーズナブルな建材を採用することでコストを抑えています。
また注文住宅と聞くと完全自由設計を思い浮かびますが、設計の自由度をあえて減らして規格化することで、設計の手間と費用を下げています。
さらに、規格化することで建材や設備に標準仕様を設け、主に標準仕様の設備を使うことを前提としているので、メーカーから大量発注によるボリュームディスカウントや、職人の工程を効率化することで、人件費も削減されているんです。
このような積み重ねによって、価格がグッと抑えられているんですね。
「安かろう悪かろう」ではない仕組みも存在
ここまで聞くと、「結局安い素材ばかり使っているから安いってことじゃないの?」という声もよく聞かれます。
しかし、ローコスト住宅=粗悪というのは一概には言えません。特に私は実際に千葉県にローコスト住宅の家を建築して住んでいますが賃貸暮らしの時よりも非常に快適な暮らしを実現できています!!
中には、ローコスト住宅ながら先ほどの努力により、建材の選定や工法に工夫を凝らし、コストを下げつつも耐震性や断熱性をしっかり保っている会社も存在します。
そういった会社は宣伝費や営業経費をカットして価格を下げているケースもあり、品質そのものには影響が出ていないことも多いのです。
ポイントは「どこでコストを削っているのか」を見極めること。見た目や設備のグレードに妥協が必要な部分はありますが、安全性や住み心地まで犠牲にしているとは限りません。
住んでわかった!リアルな「住み心地」とよくある誤解
夏暑くて冬寒いって本当?断熱性と快適性
「ローコスト住宅って、夏は蒸し風呂みたいで冬は極寒って聞いたけど…」そんな昔の住宅のような心配を持つ方も多いのではないでしょうか。
確かに、断熱材やサッシなどの仕様が標準グレードの場合、気密性や断熱性能に影響が出やすいのは事実です。
ただ、最近ではZEH基準を満たした住宅は住宅ローン控除の優遇を受けられるなどもあり、ローコスト住宅でも性能に力を入れている住宅メーカーも少なくありません。
そんな我が家もZEH基準の認定は取っていませんが、しっかりと追加コストを払ってC値とUA値を計測してもらいともに高水準と言われるレベルまで対応してもらっています。
断熱材の厚みや窓のグレードを少しアップするだけでも、室内環境はかなり変わってきまし実際電気代は私が今の住宅に引っ越す前のメゾネットタイプの賃貸住宅は70平米でしたが今の2倍弱くらいの電気代がかかっていながら室内はめっちゃ寒い状態で凍えていました、、、
工夫次第で、季節に左右されない心地よい暮らしも十分実現できるんです。
「音が気になる」「収納が少ない」…住んでみての本音
実際に住んでみると、「外の音が思ったより入ってくる」「収納スペースが足りないかも…」と感じる方もいるようですが、この騒音問題は断熱性能と結構関わっており窓がシングルガラスだったりするとダブルガラスよりも薄いので音が気になったりすると思います。
ただC値とUA値をちゃんと見ていれば断熱性能に限らず合わせて騒音も対策できます♪
収納についても安く済ませたいがあまり、クローゼットを削るとやはりモノが溢れがちになることもあります。
標準仕様内で一部屋に1つまでは標準に入っている会社や1軒に何個までは標準に入っているという会社もあり、収納はまちまちですが、もし今後子育てをしていくなどあれば収納は大いに越したことはないので、追加コストを払ってでも増やすことをお勧めします。
もし工事費が高くなる・・・ということが気がかりであればIKEAやニトリで良さげな収納ボックスも売っているので、キャッシュがたまったタイミングで収納を増やしても良いと思います!(けいは収納後付け派です)
2年半住んでみてのリアルな住み心地は別記事で書いていますので良ければご覧ください^^
「後悔した」人たちのリアルな声とその理由
よくある後悔ポイント5選(間取り・素材・設備…)
ローコスト住宅に住んだ方の後悔ポイントで多いのが以下の5つです。
- 間取りの使いにくさ
- 断熱性能の弱さ
- 収納不足
- 安っぽく見える内装
- メンテナンスコストの不安
これらは高級なハウスメーカーであれば、一級建築士のような専用アドバイザーがついてくれることと、予算もふんだんに使えるので希望を伝えれば上記を満たした家をある程度形にしてくれます。
一方でローコスト住宅は標準仕様が前提になっているので、上記のグレードや間取りに通常は制限があることが多いので自身が気にかけてハウスメーカーとともに作っていく気持ちが無ければ結構出来上がりに後悔するケースがあります。
せっかくの注文住宅だからと無駄に予算をかけ続けるのは良くないですが、注文住宅らしさも取り入れることで上記の後悔は未然に防ぐことができます。
なぜそうなった?選ぶ前に知っておきたい落とし穴
少し触れましたが後悔に陥る主な原因は2つあると思っています。
1つ目がローコスト住宅だからと言って安さばかりを追い求めてしまうこと、2つ目が設計士が結構受け身ということがあります。
ついつい「ローコスト住宅をせっかく選んだんだから」とオプションや追加コストにセンシティブになってしまいますが必要なコストはちゃんと支払うという気持ちをもって臨むことが大切です。
また施工会社によっては標準仕様から施主側から言ったことのみオプションとして加えて、言われなけば標準仕様のままに使用とする会社もあります。
実際私たちの担当の建築士の方はいい人でしたが、向こうからこれはこうした方が良いのでは?とか、ここは大丈夫ですか?という確認を逐一はしてくれていませんでした、、、
落とし穴を回避するために大事な2つのこと
後悔を防ぐにはまず「予算にバッファを設けておくこと」です。
標準仕様の金額で予算をパツパツだとどうしても満足いく設備の追加などは厳しいので、ローコスト住宅であったとしても追加コストはいくらかかけると決めておくと良いです。
その次に「優先順位を明確にすること」です。予算を取っておいても全て対応していたらいくらお金があっても足りません。
絶対に譲れない条件をはっきりさせておけば、必要なところをまず対応しておき、もし予算が余ったらそのままでも良いですし、あればよいくらいの優先順位の設備にお金をかけてもよいでしょう。
「恥ずかしい」「やばい」と思われる理由と実際の評価
世間のイメージと実際のズレ、ローコストでもおしゃれに見せられる
「ローコスト住宅ってなんか恥ずかしい…」という声、SNSなどでも見かけますよね。
昨今では住宅価格も高くなっており、都内のマンション価格は新築で1億円を超えています。そのためか、高い家=ステータスが高い、安い家=ステータスが低いという価値観を持つ人が一部にいるのは事実です。
でも現実的にはマイホームの価値は「いくら使ったか」ではなく、「どう見えているか」が重要だと思いませんか?
いくら払ってもダサければ「え?この値段でこんなのなんだ・・・」ってなりますし、逆に安くおしゃれにできていれば「この価格でここまでできるのうらやましい!」となると思います。
自分で言うのも非常にはばかられるのですが、妻のまーがWEBデザイナーをやっている知見から神は細部に宿るではないですが、高さを統一する、色は入れすぎないなどにこだわりを持って注文住宅を建築したおかげで、友人からはコスパ良いね!と言っていただけています。
実際にどうやっておしゃれにしたのかのコツは別の記事でまとめていますので気になる方はお読みください^^
外からはわからない部分も多いからこそ、先入観にとらわれすぎないことが大切ですね。
ローコスト住宅でも満足する人の共通点とは?
どんな人に向いている?ライフスタイル別の考え方
ローコスト住宅が向いているのは、「家にそこまでお金をかけたくないけど、70~80点くらいの生活質を担保したい」という価値観を持った人には最適だと思います。
たとえば、共働きで日中はほとんど家にいない夫婦や、将来的に転勤や建て替えを視野に入れている方など。
あとは住宅ローン金利が上がっている中なのでリスクヘッジの観点からも借り過ぎたくない心配性の方にも向いています。
都内の高級田和マンであれば「家=資産」がまだ現実的ですが(とはいえ仲介手数料や売買益の税金を踏まえると利益を残すのは結構難しいです)売るまでに家計が火の車になるよりも、「家=生活の場」としてとらえている人にとっては、ローコスト住宅はとても理にかなった選択肢なのです。
予算配分の工夫で満足度が変わる!
「家本体にお金をかけすぎず、その分インテリアや趣味、旅行に回したい」そんな思いを叶えられるのがローコスト住宅の良さです。
実際、キッチンやお風呂などの設備を標準にして、その分リビングの家具や照明をグレードアップしたという方も多いです。
中には、カーポートなどの外構や庭づくりにこだわって、使いたいところに予算を集中して自分たちらしい空間を作り込んでいる人もいます。
全体の予算を上手に配分することで、結果的に「満足できるマイホーム」になるんですね。
私たちもメリハリをつけることで毎日のちょっとした満足感を実感しています。
住宅メーカーの選び方と信頼できる相談先は?
ハウスメーカー選びのチェックポイント
ローコスト住宅を建てるうえで、どのメーカーを選ぶかはとても大切です。
価格だけで決めてしまうと、あとで「こんなはずじゃなかった…」と後悔することもあります。
まず確認しておきたいのは、標準仕様の内容が明確かどうか。何が基本に含まれていて、どこからがオプションなのかをしっかり説明してくれるかが信頼の分かれ目です。
標準仕様には間取りの観点(1部屋に1つのドアまでなど)と設備の観点(トイレのグレードなど)、性能の観点(断熱材など)と結構あるのでまずは標準仕様に何がどこまできめられているのか知っておくと安心です。
また、建築実績や口コミ、施工事例の豊富さも大事なポイント。ローコスト住宅のメーカーも努力をしていますが、利幅が小さいところも多いので、途中で倒産する可能性は確認しておくと良いです。
無料相談やモデルハウスで見ておくべきこと
初めての家づくりでは、知識がゼロからのスタートという方も多いですよね。
そんなときは、一括資料請求やSUUMOなどの無料相談サービスを活用するのがおすすめです。
とりあえず、どんな家が建てられるのかを知りたい方はまずは一括資料請求で興味のある住宅会社と実際に価格帯がマッチしている住宅会社複数の資料を請求して比較してみましょう。
その次に、興味のある会社に問い合わせするのも良いのですが、一括資料請求会社も万能ではないので、自分たちでネット検索して幅を広げてもよいです。
ただ住宅会社は世の中に結構多く存在するので全て調べると結局迷い続ける結果になると個人的に思っています。
私たちは資料請求の後実際に住みたいエリアのことを伺うついでにSUUMOの住まいカウンターに相談しに行きました。
住まいカウンター自体は相談料も取っていない(相談した住宅会社で契約すると住宅会社からの手数料をもらっています)のでこちらから住宅会社に聞きづらいフラットな意見を伺うことができますし、要望を伝えると価格以外の観点からいくつか住宅会社を相談してもらえました。
資料請求は大手の会社が載っていることが多く、地元のハウスメーカーはカバーされていないこともあります。
そのため、結局私たちはもともと資料で請求したところではない地元のハウスメーカーにお願いしたので意外と相談カウンターは良い選択だったと思います。
まとめ
ローコスト住宅は「坪単価30〜50万円前後」で建てられた家を指しています。
価格設定が魅力的で注目されている一方で安さに心配されている方もいらっしゃると思いますが、安く仕組みにうまく乗っかることができれば特に心配はありません。
ただ標準仕様の断熱性や耐久性、間取りなどの自由度については事前確認を怠ると後々後悔するリスクも潜んでいるので、事前の情報収集はとても有益です。
一部安い住宅はダサいや恥ずかしい(みっともない)と思う方もいらっしゃるにはいらっしゃいますが、だれからどう見られているか?よりも自分たちのライフスタイルや予算に合った家づくりをすることが重要です。
価格だけにとらわれず、将来を見据えた家づくりをしていきましょう。